アドラー心理学に『他者は「あなたの期待」を満たすために生きているのではありません』という言葉があります。部下が思うように行動しなかったり、指示や指導をしても理解してもらえない際、この言葉を思い出します。
最初は何を言っているのだろうと理解できませんでした。
「課題の分離」という考えだそうです。
自分に置き換えた表現だと理解できるようになります。
『自分は「他者の期待」を満たすために生きているのではない。同時に他者も「あなたの期待」を満たすために生きているわけでない。自分は世界の中心にいるわけでない。』
もちろん仕事ですから約束事(納期や成果)は求められますし、努力して進める必要があります。上司は仕事の進め方や取り組み方を指導していくことも重要になってきます。
ただ、そのこと(業務期待値、成果)と部下個人の課題は違うものだと認識する必要があります。
もちろん指導により期待以上の成果を上げる部下もいれば、成果を上げれない部下もいます。
例えば、成果を上げれない部下に対して「〇〇会社に対しては〇〇をもっと勉強し新しいアプローチをしたら、また〇〇業務を止めて全体業務を効率的にしたら」と指導したとします。
ある社員は指導を真摯に受け止め、自分なりに学習と業務改善に取り組みながら成果をあげます。またある社員は、昔ながらのやり方を変えるのを極端にいやがり、成果が上げれない状況が継続します。
会社的には前者は優秀社員、後者は劣等社員となり人事評価、給与にも格差が広がっていきます。
資本主義の社会では当たあり前なことです。次のステップとしては劣等社員のレベルをどうやって引き上げるかになります。
なぜこの社員は新しい手法を取り入れないのか、私の言っていることが信じられないのか?私のことが嫌いなのか?等々考えます。
その際、冒頭の言葉を思い出します。業務改善させたいのは「私の課題」、業務改善しないは「部下の課題」となります。基本、部下の課題は部下自身が気づき行動を変化させないと解決できません。
せいぜいレベルアップした際の見える景色を伝え、部下のやる気を起こさせるしかないのです。
「馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない」
自分自身も、会社にすべてを捧げて会社の期待を満たすために生きているわけでなく、「自分の期待、挑戦」を満たすために行動しています。常に水が飲みたいわけでありません。
アドラーの考えを知ってから冷静に部下に対してもイライラせずに見守り指導ができるようになりました。また自分の子供に対しても同じと考えれるようになりました。
相手の課題に対してはいくら子供とはいえ心に踏み込んで強制指導することはできません。
せいぜい水辺に連れていく行くことで気づいてもらうしかないと自分自身の気づきとなりました。
他者は「あなたの期待」を満たすために生きているのではありません
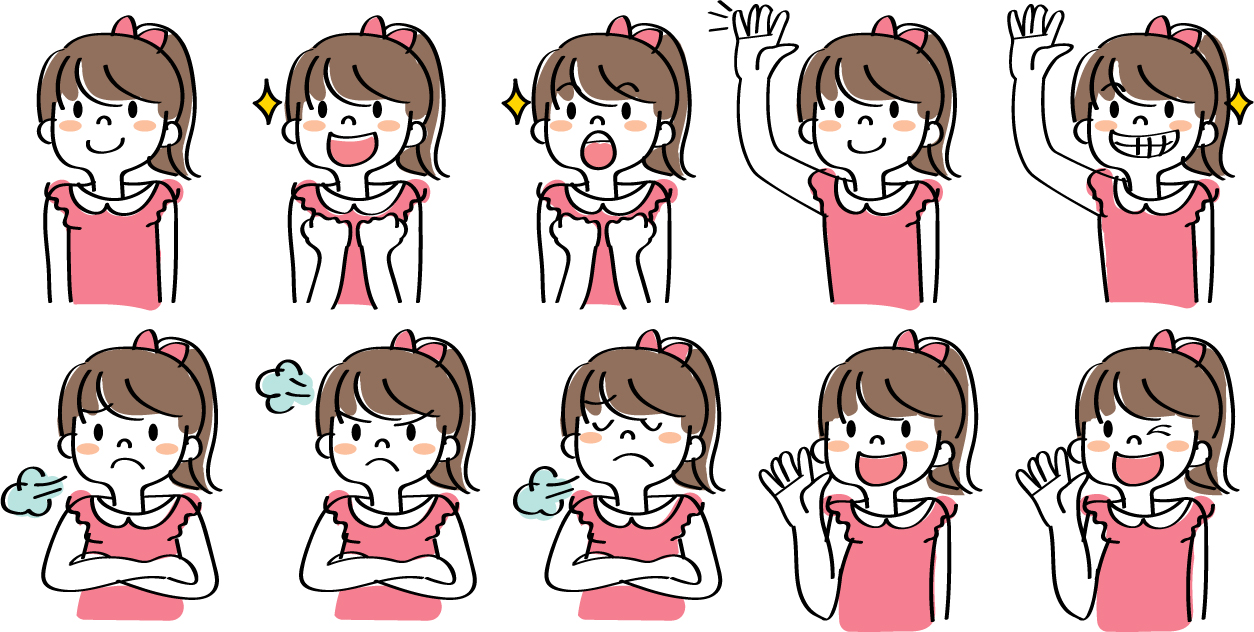 その他
その他
コメント